Duran Duran /Paper Gods
2015.9.11. 発売
良いアルバムだ。嬉しくなる。
先ずは “the tean GOOD TIMES” 代表として。
ナイル・ロジャーズ(ロジャース)は、三曲に関わっている。
共同プロデューサー、共作者、ギター:二曲
④ Pressure Off [featuring Janelle Monae and Nile Rodgers]
produced by Duran Duran with Mark Ronson, Nile Rodgers and Mr Hudson
Nile Rodgers: co-writer, guitar
⑪ Only in Dreams
produced by Duran Duran with Nile Rodgers and Mark Ronson
Nile Rodgers: co-writer, guitar
アディショナル・プロダクション、ギター:一曲
⑨ Change the Skyline [featuring Jonas Bjarre]
additional production: Nile Rodgers
Nile Rodgers: guitar
彼等らしいアルバムだ。
来年でデビューから三十五年だというのに、貫禄が「無い」。
まだ攻めている。
最前線のチャラッチャラな姿勢を崩していない。
今なお「王子様」として憧れられるだけの存在でいる。
これはたいへんな努力をもって音楽シーンに留まり続けた成果だろう。特に、レコード・デビューからずっと脱退るす事無くグループを存続させ続けてきたニック・ローズとサイモン・ル・ボンには感謝の念さえ抱く。
ジョン・テイラーのベイスがブリブリいっている。バナード・エドワーズ譲りのフレイズが以前と変わらず其処此処に出てきて嬉しいのは勿論だが、時にジョン・エントウィスルかクリス・スクワイアかという破壊的な音色で攻めてくる。
でも全体的にもう少し大きめにミックスして貰いたかった。
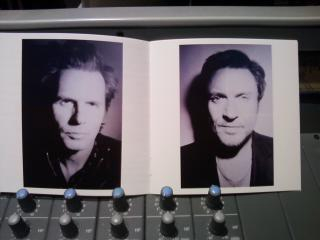
サイモンの声の色っぽさも特筆もの。上手くなり過ぎていないのも彼らしくて良い。バンドの顔である声、メロディの癖が変わっていないのはとても大切な点だろう。まだ女の子(十代~五十代の)をキャーキャーいわせようとしている志を感じる。郷ひろみ級。
飛び道具としてのシンセがとてもニックだ。おそらく「狙い」として、16ビートでオクターヴ幅を上下したり、フェイザーがクワ~ンとかかる、初期っぽいシークエンス・パターンを入れている曲があるのも、昔からのファンには堪らない筈。
そしてそれが、今世紀に入ってのテクノやEDMと親和性の高いものなのだ、という事を主張している。例えばダフト・パンクやパフュームがこのオケで歌っても全く問題が無い。その現役っぷりに感服。

音楽的な貢献という意味で、ロジャー・テイラーは昔からあまり強い色を感じさせないけれど、彼が脱退していた時期(『ノトーリアス』以外)のドラム・パートが、マシーン或いは打ち込みっぽい音処理が施されていた事を思うと、彼のドラムズはとても特色があるものだという事に気付く。
まぁ最近は細かく直されているのかも知れないけれど(これはドラムズに限らないが)、「プラネット・アース」からの数年間、ジョン、アンディ・テイラーとのリズム・セクションの少し(いや、かなり?)背伸びをしたファンキーなリズム・パターンは彼等の大きな魅力だった。初期ロクシー・ミュージックやエアロスミス、レッド・ゼプリンに似た、「ぎこちなさ」を個性にしたアンサンブルだったのだと思う。それは『ノトーリアス』以降、彼とアンディが復帰する迄、失われていた。アンディは直ぐに抜けたが、ジョンとロジャーのコンビはまだその個性を継承していると思う。
僕は彼等やワム!、カルチャー・クラブを、第二次ブリティッシュ・インヴェイションという人気の面だけでなく、英国白人ファンクとして「AWB、イアン・デューリー&ザ・ブロックヘッズとヘアカット100、ザ・スタイル・カウンシルの間」という系譜上でも共通項があると考えている。しかし他の多くがアフリカ系やジャメイカ(=もと英領)といった本場のミュージシャンをメンバーに迎えていた中、デビュー時のDDはぎこちなくても構うこと無く「英国白人による黒人音楽解釈」をテーマの一つとして据えていた。徹底して(ギャグ/悪趣味寸前の)カッコつけをしつつ。これはロクシー・ミュージック、ジャパンの系譜でもあるのはデビュー当時から指摘されていた通り。彼等もそれを隠さなかった。
本作は多彩なゲストも話題だが、何よりバンドらしさを感じさせるアルバムになっているのが、長年のファンにとっては嬉しいのではないだろうか。
冒頭で「王子様」と書いた。王様として君臨する気が無いのだと思う。大御所なんて御免だぜというか、新御三家とは距離を置いていたジュリーというか、横綱ではなく常に大関・関脇キープというか、まあそんな感じ。
貫禄が無いと書いた。しかし余裕はある、余裕綽々であるという事を加筆しておこう。時代の追い風を強く強く感じている筈だ。大いに話題となって、大ヒットをして貰いたい。
あの「ニュー・ロマンティクス」という時代を象徴しているバンドなのは確かなのだけれど、象徴し過ぎて古びて了う事は上手く回避出来ている。
大体、九十年代にもヒットを飛ばしたのだし(あれも嬉しかった)、解散していた時期も無いのだから。
同世代を見回しても、下の世代と比較しても、彼等が「現役」としてずっと世間の注目を浴びている点は称賛に値する。
調べてみたら、今回の五年というブランクが最も長く、それ以前は長くても三年というペイスで新作を出し続けている。「継続は力なり」という使い古された言葉が似合う、なのにヴェテランっぽさの無え「現役のチャラッチャラ兄ちゃんども」であるのが本当に面白い。
ナイル・ロジャーズを迎えてトゥアーを行うという。来日懇願。心から懇願。
日本盤にはボーナス・トラックが四曲。世界で最も収録曲が多いそうだ。その最後に入っている⑯ Northern Lights がウンペペものなのも堪らない。
ナイルが不参加という事もあってか、シークよりもロッド「アイム・セクシー」を思い出す。それもまたチャラい。その最後から、三十四年遡ってデビュー曲「プラネット・アース」に戻っても不自然さが無い。音楽性というよりも、何よりも先ず「姿勢」が変わっていないからだろう。脱帽。
ニック・ローズがニヤニヤと(目と口の端っこだけで笑う)勝ち誇っている顔が浮かぶ。
人見 “HTM48” 欣幸, ’15. (音楽紹介業)


コメント